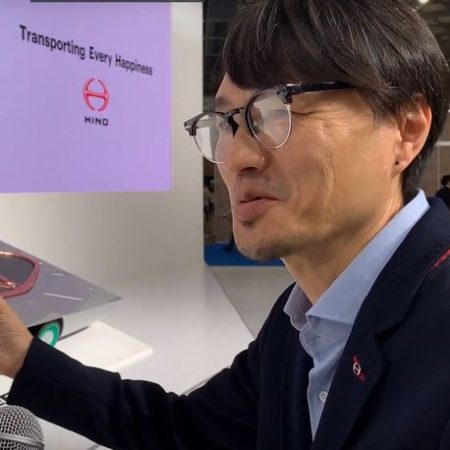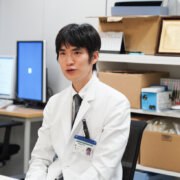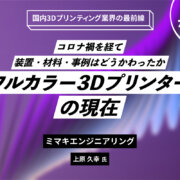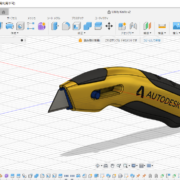自動車業界の3Dプリンター活用の現状と将来

数年前には試作品への適用がメインだった業務用3Dプリンターですが、その技術開発が進むにつれて徐々に完成品の開発にも用いられるようになりました。特に自動車業界では、成熟した市場での競争力強化に向けて、3Dプリンターでの量産品製造に取り組んでいます。
この記事では、自動車業界で3Dプリンターがどのように活用されているか、将来はどうなっていくのかについて紹介します。
自動車業界では試作品からオーダー、台数限定モデルで活用
自動車業界では、ほんの数年前まで試作品の製造にとどまっていた3Dプリント技術を純正のオーダー品や台数限定モデルに適用し始めています。ここでは、トヨタ自動車とブガッティの2社が取り組んだ事例を紹介します。
スープラの復刻純正部品を3Dプリンターで製造 | トヨタ自動車
『道が人を鍛え、クルマを鍛える』ラリーやロードレースといった極限状態において生み出された技術を一般車両開発にフィードバックする役目を負ったトヨタ自動車のレーシングチーム「TOYOTA GAZOO Racing」。同チームは、すでに販売を終えて入手が困難になっていたA70スープラ、A80スープラの補給部品を復刻し、純正部品として再販売しました。販売数は限られており、注文が入り次第製造をするオーダー品となっています。
今回復刻される部品には、クラッチ関連やエンブレム、ボディー部品などがありますが、本来金型などが必要な部品も含まれています。すでに廃版となり金型がない状態で部品を製造すると、気軽に購入できるような金額ではなくなってしまいます。
今回TOYOTA GAZOO Racingは、3DプリンターのサービスビューローSOLIZEやサプライヤーと提携し、一部の復刻部品を3Dプリンターで製造したのです。3Dプリンターの採用によって少量生産に対応でき、ユーザーの要望に沿った復刻部品を無理のない価格での提供を可能にしました。
今後も3Dプリンターを活用した復刻部品の種類を増やしていくと考えられます。
台数限定のスーパーカーを3Dプリント技術で実現 | ブガッティ
イタリアの自動車メーカーであるブガッティは、一般道では走行できないサーキット専用のハイパーカー「Bolide」を限定40台で市販化すると発表しました。日本円で5億円を超えるハイパーカーには、3Dプリンターで生産されたパーツが多く使用されています。
ブガッティが最新の3Dプリンティング技術を用いてBolideのパーツを開発した目的は、超軽量・薄型・超剛性を両立したパーツを実現するためです。チタンなどの軽量で高強度の材料を用い、複雑な3次元構造の自動車部品を3Dプリント技術で製造しています。
ブガッティはチタン製のパーツだけでなく、チタンとコイル状のカーボンというハイブリッド素材を組み合わせ、3Dプリントされたパーツの開発にも成功。独自に研究開発を進めている3Dプリンティング技術が、ブガッティの強みになっています。
付加価値の高い優れた性能を持つ自動車部品を製造し、それを用いてスーパーカーを実現する流れは、ブガッティ以外の海外自動車メーカーでも進められています。そのキーとなる技術として、各社は3Dプリント技術の開発・適用に積極的に取り組んでいます。
自動車業界における3Dプリント技術の将来性

近年の自動車業界における完成品への3Dプリント技術適用として、トヨタ自動車とブガッティの事例を紹介しました。従来から用いられていた試作品の枠を超えて、完成品への適用が実現しています。
これは、3Dプリンターの造形技術が飛躍的に進歩したことにより、デザインの自由度が増し、複雑な部品でも違和感なく製造できるようになったことが要因の一つとして挙げられます。数年前の3Dプリンターのイメージにあった、造形する際の層が明確に分かるようなことはありません。
一方で、トヨタ自動車の事例は受注生産によるオーダー品であり、ブガッティの事例は限定40台の高額なスーパーカーへの採用です。まだ各社共に、広く販売されるような量産品への適用は実現していないのです。
これは、生産量とコストのバランスの観点で量産品には金型を用いたプレス加工や切削加工、鋳造など従来の製法の領域に3Dプリンターの技術進化がまだ追いついていないことを意味しています。しかしながら、こうした大手自動車メーカーよりも先んじて、最終部品の製造・販売を開始しているサードパーティと呼ばれるアフターパーツメーカーも海外に存在します。世界でもトップクラスの自動車メーカーであるトヨタ自動車のこうした動きが最終部品としての実用化に結び付いたとき、市場は大きく動くものと思われます。
今後も自動車業界では、3Dプリント技術で製造された完成品は増えていくでしょう。しかし、この先数年間は、オーダー品や付加価値の高い部品など限られることが予想されます。
販売台数の多い車両に採用される量産品に適用するためには、従来の加工法に対して生産量とコストのバランスで優位になる必要があります。
造形時間の大幅な短縮や適用可能な材料の拡大など、ここ数年で3Dプリント技術は大きく進化しています。これらの技術を活用し、自動車部品製造に最適化することで、そう遠くない未来に3Dプリント技術を中心に作られた車両を、多くの人が気軽に購入できる時代がくるかもしれません。
まとめ
数年前までは試作品にしか使われていなかった3Dプリンターですが、現在ではトヨタ自動車やブガッティを始め、完成品に使われ始めています。数年間で生産の自由度や3Dプリンターで造形できる部品の複雑さ、デザイン性などが向上したことが要因です。
3Dプリント技術は年々進歩し続けているため、新しく開発された技術を自動車部品の製造に最適化することで、生産量とコストのバランスの実現が期待されます。
今はまだ、オーダー品や台数限定のハイパーカー向けで、大多数の人は3Dプリント技術で製造された自動車を入手することは困難です。できるだけ早いタイミングでの実現が期待されます。